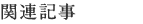ピクニックを楽しむ社員たち。大橋鎭子は、サングラスに水玉のバンダナ姿。その左隣が花森安治
いよいよ、出版の世界に足を踏み入れた常子。編集会議のさなか、男性部員のお茶を替えようとしたら、もっとやるべきことがあると、谷編集長に諭されます。
「君の意見はないのかい?」「作りたいと思う企画が浮かんだら、ぜひ聞かせてくれ」
男性の上司から、初めて対等に扱われた常子は、感激し、一生懸命に初企画を考え始めるのです。
翻って、大橋鎭子。
1946年、26歳の若さで出版社を起こそうと決めた彼女は、編集長となる花森安治に、こう語ります。
「わたしは、女の人が自分の力を充分に発揮できる会社を作りたいのです」
「女性の活用」といったフレーズが聞かれる昨今ですが、70年も昔に、そんな理想を真剣に追い求めていたのですね。
かつての『暮しの手帖』編集部には、みんなが残業するときの夜食を準備するといった「当番」がありましたが、それは男性だからといって免除されることはありませんでした。
給与面の待遇も、男女の差別なし。
女性も男性も、みんなが自分の暮らしの知恵や実感を持ち寄り、とにかく手を動かして、わいわいと賑やかに作ってこそ、『暮しの手帖』なのです。大橋が思い描いた雑誌作りの夢は、いまも変わらず、わたしたちのなかに生きています。
(担当・北川)