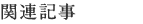「あたらしさ」と出会いたい
——編集長より、最新号発売のご挨拶
各地で梅雨入りし、むしむしする日が続きますね。お元気でお過ごしでしょうか?
この「ご挨拶」を書くのは、いつも発売の数日前なのですが、今日は雨のなか、京都へ向かう新幹線で書いています。新幹線に乗るのは、ほんとうに久しぶり。京都で暮らす、ある作家の方のもとへ、次号の表紙の原画を受け取りに伺うのですが、どんな絵なのか、とっても楽しみです。
いま、私の目の前には、できたてほやほやの最新号があります。表紙画を手がけてくださったのは、画家の今井麗さん。大きく豪快にカットされたメロンに、うっすらと透けた生ハムがのった食卓の情景は、鮮やかで、初夏のよろこびが生き生きと伝わってくるよう。
モチーフの「生ハムメロン」は、今井さんの幼少期の、ある思い出と結びついています。ちょっと意外で愉快なエピソードは、169頁に今井さんが寄せてくださった文章でお楽しみください。

今号の始まりの記事「わたしの手帖」には、「毎日があたらしいから」というタイトルをつけました。
主人公は、ピアニストの舘野泉さん。ご存じでしょうか、 20代でフィンランドに渡り、世界中でコンサートを開いて活躍。60代半ばに脳出血で倒れ、右手が使いにくくなるものの、左手だけでピアノを奏で、84歳のいまも現役でいらっしゃいます。
きっかけは、昨年11月10日に東京オペラシティで開かれた、演奏生活60周年のコンサートにお伺いしたことでした。プログラムを開くと、「苦海浄土」といった言葉のつく難解そうな曲名が並び、ほとんどの曲に、「※世界初演」と添えられています。自粛生活のなか、生の音楽に久しぶりに触れたくて足を運んだのですが、正直なところ、「理解して楽しめるかなあ」と不安がよぎりました。
ところが、いざ演奏が始まると、これがもう、とにかく素晴らしいのです。耳なじみのないメロディの流れに身をひたしていると、どこか知らない土地に運ばれて、シュールかつ美しい風景を目にするよう。「左手だけで弾いている」なんて、すぐに忘れて没頭していました。
ああ、音楽の力って、すごいな。84歳になっても、こんな「あたらしい曲」に挑める舘野さんって、どんな方なんだろう。
単純ですが、いつもだいたいそんなふうにして、記事は生まれていきます。
東京のご自宅でお会いした舘野さんは、飾らず、偉ぶらず、なんともチャーミングな方でした。脳出血で倒れ、リハビリを経て復活を遂げた話は、言葉を探しながら誠実に答えようとしてくださる。妻で声楽家のマリアさんとの馴れ初めや、日々の炊事の分担、ときどき勃発する夫婦喧嘩の話は、ユーモラスに。
とりわけ印象的だったのは、「脳出血で倒れたときよりも、コロナの影響でコンサートができない時期のほうが辛かったかな」とおっしゃったことでしょうか。音楽は、聴く人たちと心を通い合わせるように、会場が一体となって完成されるもの。コンサートのステージに立つと、自分でも知らなかった音が鳴り、「あたらしい自分」が生まれるのだと。
いまは、誰もが息苦しさを覚えつつ、それぞれの暮らしの小さなよろこびを心のよりどころにして、日々を歩んでいるのではとないかと思います。
舘野さんのように、毎日「あたらしい自分」であり続けるのは、とてもむつかしい。それでも、考えること、深く感動すること、自分の思いを言葉にすること、他者を思いやることを忘れずにいたい。そんなことを考えながらこの記事をつくり、一冊を編みました。
今号より、料理家の枝元なほみさんによる新連載「食べる、生きる、考える」が始まります。「台所の窓を開けて社会とつながりたい」と語る枝元さんが、社会のどんな部分に疑問を抱き、少しずつでも変えたいと願っているか、その柔らかな語りに耳を傾けて、ご一緒に考えていただけたらと思います。
そのほかの記事も、担当者が明日から一つずつご紹介していきますので、ぜひお読みください。
あっという間に、京都に到着です。どうか、みなさまの毎日が、健やかで、あたらしいよろこびに満たされますように。
『暮しの手帖』編集長 北川史織