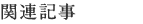敗戦から78年。私たちが、戦争の記憶と向き合う機会を失くさぬように。当事者でなくても、たとえ想像が追いつかなくても、メッセージを受け取った私たちが「語り継ぐ」ことで、何かを変えられるのなら。
『暮しの手帖』初代編集長の花森安治が、夏に足を運んだ場所が「千鳥ヶ淵戦没者墓苑」でした。花森はその場所を「無名戦士の墓」と題し、文章を綴りました。下記より、その全文をお読みいただけます。
***
無名戦士の墓 文・花森安治(『暮しの手帖』初代編集長)
もう町中どこでも、朝から夜中まで、年中ぶつかりあい、ひしめきあい、ごったがえしているこの東京の、しかも、そのまっただなかに、ポカッとこんなところがあるというのは、なんだかウソみたいな気がする。
一万五千平方メートル(四千七百坪)のだだっぴろい敷地は、ざっと見わたしたところ、人っ子ひとり見えない。敷きつめた砂利の一つ一つまでが、きちんと真夏の午後の太陽の下でしいんとしずまりかえっていて、いちめんのセミしぐれである。どこもかしこも、やけに明るいのである。そして、涼しい風が吹いていた。無名戦士の墓地である。
……兵隊たちは、ひとりのこらず、小判形のシンチュウの小さい札を持たされていた。両はしの穴にヒモを通して、肩からじかにはだかにかけていた。札には部隊記号とその兵隊の番号が乱暴にうちこんであった。
フロに入るときでも、どんなときでも、はずしてはならぬと命令されていた。野戦ではフロなどめったに入れぬから、白いもめんのヒモはすぐにどすぐろくよれよれになり、うちこまれた数字にはアカとアブラがこびりついていた。
戦死したとき、身元を確認するためのもので、「認識票」というのが正しい呼び名だったが、兵隊たちは「靖国神社のキップ」と言っていた。
……この墓地は、皇居のお堀に向きあっていて、英国大使館のまえの青葉通り、都電なら三番町の停留所から、だらだらと千鳥ケ淵の方へ下ったところにある。小さな札が出ているが、無名戦士の墓とは書いてない。「千鳥ケ淵戦没者墓苑」である。ふらっとやってきた高校生が、事務所で「おじさん、ここはなんの古戦場ですか」と聞いたという。
歩きにくい砂利道を上ってゆくと、横に長い前屋があり、その柱のあいだから向こうに六角堂がみえる。美しいつり合いである。六角堂の中央に、アジアの各地から集めた石で焼いた陶棺がすえてある。そばの台に小さい草花の束がいくつかおかれて、「一束十円」という文字が添えられている。
ここへくる人は、一日に百人をこえることはあまりない。しかも、この六角堂におまいりするのは、そのうちの一割あるかなしかだという。
……兵隊たちは、歩きつかれてくると、食べものの話と、家に帰る話をした。ここから日本へ帰るにはどうしたらよいかを、大まじめで研究した。いつもぶつかるのは海であった。陸地はなんとかたどってゆくことにしたが、朝鮮海峡までくると、それまで活気のあった会話が、いつでもポツンと切れた。だまりこんで疲れた足をひきずりながら、ああ帰りたいな、とおもった。
そんなとき、ひょっとハダの認識票が気になることがあった。「靖国神社直行」、日本へ帰るいちばんの早道にはちがいなかった。
……この無名戦士の墓を作ることは、昭和二十八年の閣議できまっていた。しかし、工事がはじまったのはおととしの三十三年、そして去年の春、やっとのおもいで出来上がった。工費五千七百万円、建物は谷口吉郎氏、庭は田村剛氏の設計である。
出来上がった日には、天皇と皇后がおまいりになった。大臣も参列したろう。しかし、それっきりであった。
外国には大てい無名戦士の墓があって、各国の元首や首相級の人物がその国を訪れると、必ずおまいりするのが儀礼である。まえの首相岸信介氏が外遊したときも、もちろんそうしてきたが、出かけるまえ、日本の無名戦士の墓にまいってくれとたのんだら、忙しいからと花束だけをとどけてよこした。
きまったお祭りの日があるわけでもない。憲法記念日とおなじで、作ることは作ったが、作りっぱなしである。
……古風なことを言うようだが、人間には、やはり、その人そのひとに持って生まれた星というものがあるのだろうか。
兵隊は、みんな家に帰りたかった。そして帰ってきた者もある。帰ってこなかった者もある。
五年ほどまえの、押しつまった年の暮れ、千葉の稲毛にあった復員局の分室を訪れたことがある。荒れはてた構内の枯れ草のなかに、もとの部隊の弾薬庫があって、うすぐらい中に、天井までぎっしり遺骨がつまっていた。灯明に火が入ると、どの箱にも「無名」と書いてあった。全部で二千五百柱だと聞かされた。
みんな名前があったにちがいない。それが役所の戸籍も焼け、連隊区の兵籍簿もなくなってしまったのだろう。そして一目でいいから会いたかった家族も、死んでしまったのかもしれない。
シンチュウの認識票など、なんの役にも立ちはしなかったのだ。この兵隊たちは、靖国神社にさえ入れてもらえないのだ。名ナシノミコトでは、まつることができないのだそうだ。
……そのために、この無名戦士の墓を作ることになったのだが、そうときまってからも、なかなかできなかったのには、いろいろ裏があったということである。
一つは靖国神社の反対だったという。戦後、ここも単なる一「宗教法人」になって、国からは一銭も出してはならぬことになった。それなのに、無名戦士の墓に何千万という金を出すとは何事であるか、ということだったらしい。
無名戦士の墓ができ上がると、外国の例のように、国賓がそちらへおまいりするようになるだろう、それではこっちはどうなるんだ、ということもあったのかもしれない。
政府がそれで弱腰になって、作ることは作ったが、あとは知らぬ顔をしていることになっているのかもしれない。
……名前がわからないから、生きていたとき、どんな暮しをしていたひとたちか、わかるはずはない。
わかることは、大部分が、たった一枚の赤紙で、家族と引きさかれてしまって、それっきり死んでしまった兵隊たちだということである。おなじ兵隊でも、えらい将校なら、死んでも名前がわからぬことはあるまい。屑ラシャの黄色い星が、ひとつかふたつか三つ、つまりただの兵隊だったにちがいない。ひまさえあると、家に帰ることばかり考えていた兵隊たちのうちのだれかなのだ。
……その人たちは帰らなかった。おなじ兵隊のひとり、ぼくは帰ってきて、それから十五年も生きて、いまこの人っ子ひとりいない妙に明るい墓地に立っている。
そして、人には持って生まれた星があるのかと古風なことを考えている。こうして生きて帰った者もあるし、死んで帰ってきた者もいる。死んで靖国神社にまつられているものもあれば、名もわからず弾薬庫のすみにおかれ、やっと墓が出来ても、国も知らん顔、だれもかえりみようとしない者もある。(こんな国ってあるものか)
この墓には、どういうわけか一字も文字が書かれていない。しかし「祖国のために勇敢に戦って死んだ無名の人たちここに眠る」といったふうの言葉だったら、むしろ、なんにもない、このままの方がよい。
どんなに帰りたかったろう。ぼくならそう書いてあげたい。あすは、十五年目の八月十五日である。
***
初出:『朝日新聞』日曜版「東京だより」(朝日新聞社・1960年8月)
収録:『一銭五厘の旗』(1971年10月刊)
『花森安治選集 第3巻』(2020年11月刊)