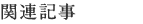悲しみは、ちから
(11号「詩が悲しみに寄り添えるなら」)
こんにちは、編集長の北川です。
いつからか、電車に乗って前に座る人びとを眺めるときなど、
「この人たちも、きっと、誰かを失った悲しみを抱えて日々を送っているのだろうな」
という思いが胸をよぎるようになりました。
自分も、身近な人を亡くす経験をいくつか積んで、ふとした瞬間に思い出すと、涙がにじむようなことがあるからかもしれません。
一方で、その人が生きている間にかけてくれた言葉、分かち合った何気ない出来事が、光る小石のように胸の底に確かにあって、ときに自分をあたためてくれるようにも感じています。
この企画は、東日本大震災から10年が経つことに思いをめぐらせて生まれました。
あのとき、多くの人が大切な人を失い、大切な場所を失いました。
「被災地」と呼ばれる土地の多くは復興しつつあると報じられていますが、目に見えるものが取り戻され、年月が過ぎれば、人の心は癒えてゆくものなのでしょうか。
もちろん、同じ災害で、同じく家族や近しい人を失ったとしても、その経験と悲しみは人それぞれであり、同じであるかのように語ってはならないでしょう。
さらに、この10年の間にも、各地で起こったさまざまな災害によって多くの「いのち」が失われ、いまは未知のウイルスが暮らしに影を落としています。
私たちは、人生に降りかかる「悲しみ」の経験にどう向き合えばいいのか。悲しみは、どうしたら癒やせるものなのか。
そんなことを、批評家で随筆家である若松英輔さんとお話しするなかで、若松さんは、こんなふうにおっしゃいました。
「何かを失って悲しみ、苦しむというのは、それだけ、愛すべきものがこの世にあったということですね」
「悲しみは、一人ひとりで違う、固有のものですが、人は悲しみを抱くことで、共振、共鳴できるように思います」
「よく、『悲しみをちからにする』といった言い方をしますが、それはやや違っているように思います。おそらく、悲しみこそが、生きるちからであり、私たちを明日へと運んでくれるものなのです」
そんなやりとりを経て、今回、若松さんが綴ってくださったのは、ご自身が喪失の深い悲しみから否応なしに詩を求めるようになり、10年の歳月のなかで見いだしていった、「悲しみに寄り添う詩のちから」についての随筆です。
たとえ、詩になじみがなかったとしても、失う悲しみを経験した方であれば、「ああ、この感覚はわかる」と胸に落ちるものがあることでしょう。
一人ひとりが人知れず抱えている、その固有の悲しみと、心静かに向き合うために。ぜひ、お読みください。(担当:北川)