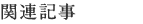暮らしもひとつのアートになる
――編集長より、最新号発売のご挨拶
このところ、6時くらいに目覚めると東の空が明るく、気持ちまで晴れやかになります。寒さ厳しい日々ですが、確実に、季節は春に向かっているんですね。いかがお過ごしでしょうか。
今号の表紙を目にされたら、懐かしいような、切ないような気持ちで、胸がきゅっとなるかもしれません。絵本作家の酒井駒子さんによる、「いちご」。幼い子が、家族で食べようと洗って置いてあったいちごを、無心に食べています。自分も、わが子も、こんな時期があったのだなあ。いや、もしかしたら、いまちょうどこんな情景が身近な方もいらっしゃるかもしれませんね。
編集部員のなかにも働く親は多く、感染拡大によって、休園となる保育園も増えていると聞きます。先の見えない日々が続くと、心身がじわっと疲れてくるものですが、毎日のおだやかな暮らしが、私たちを支える「確かなもの」であってほしい。今号は、そんな思いを込めて編みました。
巻頭の記事は、写真家の茂木綾子さんの歩みを紹介する、「結んで、開いて、旅をする」。思えば、この記事の取材で淡路島を訪ねたのは、昨年の9月半ばのことでした。
神戸の舞子駅で電車を降りて高速バスに乗り換え、少し走ると、透明感のある海がひろがる景色が続きます。ああ、きれいだなあ。茂木さんは13年前、スイスから家族4人で淡路島に移住し、廃校を改装して「ノマド村」を開きました。ノマド、すなわち「遊牧民」に自身をなぞらえる茂木さんは、ここを地域の人びととアートを分かち合う場にしようと考えたのです。
ところで、コロナ禍となってから、「芸術は不要不急か」という議論があり、私たちはこれまでになく、アートが自分の人生にもたらす力について考えることとなりました。自分のことを振り返れば、自宅に一人こもって仕事をしていた時期、手もとにある絵や写真集を観ることで、心を遠くへ飛ばすことができました。気持ちがざわざわと落ち着かないときは、バッハの『無伴奏チェロ組曲』をずっとかけていたことも思い出します。11号の取材で、南桂子さんの銅版画をたっぷり観られたときのうれしさといったら。アートはけっして不要不急ではなく、やっぱり必要なんだと実感したと言えばいいでしょうか。
今回の記事を編むにあたり、私が茂木さんの話に耳を傾けながら考えたのは、「アートが地域にもたらすものって何だろう」ということでした。いっとき、バブルの頃までは、日本各地に立派な美術館などの「箱物」がつくられましたが、そこに「魂」がないと、つまり、いまを見つめてアートを生み出す人、よりよいかたちで提示できる人がいないと、それはただの「箱」になってしまいます。
茂木さんと夫のヴェルナーさんが築いた「ノマド村」は、立派な「箱物」ではなく、周囲の人たちと土壁を塗るなどしてつくり、手の跡や体温を感じさせる「居場所」でした。ここで暮らしながら、アートを分かち合うって、どういうことなのか。その答えは、「結んで、開いて、旅をする」というタイトルに込めましたので、ぜひ、お読みください。
そのほか今号は、「『手前味噌』は楽しい」「ハーブの香る暮らし」「アイロンがけのおさらい」「こてらみやさんのDIY」など、暮らしのなかで手を動かす楽しみをたくさん提案しています。
ともすれば、暮らしは繰り返すうちに、マンネリ化して澱んでしまったりするものですが、そこに新たな風を吹き込み、まっさらな目で見つめて、自分の手を動かして楽しんでみる。それができたなら、暮らしもひとつのアートになるのではないかと思うのです。
みなさまの大切な暮らしのなかで、この一冊が少しでも心を潤し、お役に立つものでありますように。どうかお身体を大切にお過ごしください。
『暮しの手帖』編集長 北川史織