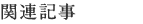いま、言葉を信じたい
――編集長より、最新号発売のご挨拶
梅雨が抜けきらないなか、全国で新型コロナウイルスの感染者数が増えつつあり、どうにも気持ちが落ち着かない日々が続きます。いかがお過ごしでしょうか?
過日は、九州地方をはじめとする各地で、豪雨によりたくさんの方々が被害に遭われました。心よりお見舞い申し上げます。ご不便が一刻も早く解消され、そして、深い苦しみや悲しみが少しでも癒されますように。
私たち編集部は4月から在宅勤務態勢に入り、それはいまでも続いています。最新号は、撮影を始めようとした矢先に「緊急事態宣言」が出されたため、ある企画は内容をがらりと変更し、いくつかの企画はギリギリまで撮影を日延べして、さらに発売日を7月25日から29日に延ばすことで、なんとか発行まで漕ぎつけました。
いつもよりもお待たせしてしまい、申し訳ありません。
最新号の大きなテーマは、「暮らしから平和を考える」。このテーマを考え始めたのは、確か昨年の10月あたりのことで、私の頭にあったのは、「戦争と平和」、そして「台風への備え」くらいでした。まさか、世界中の誰もが同じ困難と向き合い、「平和」の希求がこんなに切実なものになろうとは、思ってもみなかったのです。
正直に言えば、「撮影ができないかも」となったとき、過去の料理記事などを再編集して頁をつくろうかとも考えました。それだって、みなさんのお役に立つのなら、決して悪くはない手段ですよね。
でも、なぜだろう。私はどうしても、新しくつくった記事を載せたかったのです。いま、みなさんと同じ空気を吸い、この苦しみを味わっている私たちが、できる限りの、精一杯のものをつくって差し出す。ちょっと見栄えは冴えなくなるかもしれないけれども、それが大事かもしれない、そう思いました。
じつは私自身が、このコロナ禍のなかで大きな不安に押しつぶされそうでした。まだ感染の危険があるなかで、スタッフを撮影に送り出していいのだろうか、という迷い。ビデオ通話での打ち合わせはしているにせよ、会わずに進めることでコミュニケーションに齟齬が生じ、ひいてはそれが出来上がりに響くのではないか、という焦り。
どんな状況下でも、なるたけいい本をつくって、きちんと売りたい。いや、売らなければ、制作は続けていけない。世間でよく言われる、「いのち」と「経済」のどちらが大事なんだ? なんて問いかけは、答えようのないものとして重く胸の底に沈んでいました。そんなのは、どちらも大事に決まっているじゃないか。
みなさんのなかにも、そう心のうちで叫んだ方はいらっしゃるでしょうか? 私たちは、正解が一つではない世界を、迷いながら、悩みながら、歩んでいるんですよね。でも、なんとか自分で道を選んで、歩んでいかなくちゃいけない。それがおそらく、暮らしていくこと、生きていくことだから。

今号の巻頭は、「いま、この詩を口ずさむ」という特集としました。6編の詩と、それに寄り添う写真や絵で構成する、いたってシンプルな頁です。
夜更けに食事をつくってテレビをつけると、街角で、この数カ月の困窮をぽつりぽつりと語る人がいます。一方で、そんな他者の生活苦を顧みないような軽々しい言葉、あるいは、なんだか格好いいけれども実のない言葉を発する政治家がいる。SNSをちらっと覗いてみると、「それ、匿名だから言えるんじゃない?」と思うような、毒々しい誹謗中傷が飛び交っている。
言葉って、こんなふうに使っていいものだったっけ。ふと思ったのです。人をまっとうに扱うように、暮らしを自分なりに慈しむように、心から誠実に言葉を発していきたい。たとえ不器用でも、言葉は完璧じゃないとわかっていても。ここでは、そんな思いを呼び覚ましてくれる詩を選びました。
たとえば、黒田三郎の「夕方の三十分」は、いまで言うワンオペ育児をするお父さんと、その娘が繰りひろげる、夕餉の前のひとときを描いた詩です。ウィスキイをがぶりと飲みながら、玉子焼きなどをつくるお父さん(飲酒しながら火を使うのって、ほんとうはダメですが)。そんな父の作業をたびたび邪魔して、しかもだんだん口が悪くなる幼い娘。ふたりはいさかいを起こします。
どんな家でも見られそうな情景ですが、最後の数行を読むと、心がしんとします。ああ、暮らしって、親子って、こういうものじゃないかと思う。ぜひ、島尾伸三さんによるモノクロームの写真とともに味わってみてください。「このところ、しゃべる機会がめっきり減って、口のまわりの筋肉が凝り固まっているようだ」という方(私がまさにそうですが)、音読することをおすすめします。
最後に。今号の表紙画は、画家のミロコマチコさんに描き下ろしていただいた「月桃の花」です。
自分でも意外なほどすっかり落ち込んでしまっていたとき、「心を照らすような、希望を感じさせてくれるような絵を描いていただけませんか」と、ただそれだけをお伝えして待ちました。この絵が奄美大島から届いたときのうれしさと言ったら。「なんだか、魔よけみたいだね」とみんなで言い合ったものです。
いまは、この号を傍らの本棚に立てかけ、ときどき表紙に目をやりつつ、次の秋号を制作しています。取材・撮影がふつうにできること、人と会って言葉を交わせることは、なんてうれしく、ありがたいんだろうと思いながら。私たち一人ひとりが、決して完璧ではないけれども、それぞれに愛すべき暮らしを抱えながら。
つまずいても、悩んでも、日々は続いていくのですね。どうかみなさん、お元気で。心身をいたわって、すこやかにお過ごしください。
『暮しの手帖』編集長 北川史織