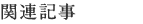『星の子』 今村夏子 著
朝日新聞出版 1,400円+税 装釘 田中久子
この作品は家族と宗教を題材に、人が何かを、そして誰かを「信じる」ってどういうことなのか、主人公の成長を通して描かれる物語として読みました。
主人公のちひろは生まれつき病弱で、娘を助けようと手を尽くす両親は、新興宗教にすがります。やがてちひろは健康に育っていき、両親は、「金星のめぐみ」という「宇宙のエネルギーを宿した」高価な水のご利益だと、ますます信仰にのめり込んで、世間からは異質な人たちとして見られます。
物事を見る目が変わったり、恋愛をしたりと、成長していくちひろ。その宗教に対しては、態度を留保するようになりますが、両親に対しては、心から大切に思う気持ちを持ち続け、疑うこともありません。ちひろの姉は、世間と同じ目を持つようになり、高校1年生にして家を出て行ってしまいました。親戚は両親からちひろを引き離そうとします。
物語の後半、ちひろにもその新興宗教への懐疑の念の兆しが見え、両親への気持ちにも変化が表れます。両親と宗教と世間との関係のなかで、疎ましさを感じたのか、例の水を自分に施す両親を邪険にしてしまいます。
そして、終盤、家族3人で参加した教会の研修旅行の間、別行動になった両親とちひろは、会いたいのになかなか会えません。やっと会えた3人は、同じ流れ星を一緒に見ようとしますが……。
両親は娘たちのことを愛し続けます。だから、この後訪れるであろう、ちひろとの別れを惜しんだのだと思います。でも、客観的な目を持ち始めたちひろは、不安定に揺れています。大切な人が信じるものだからといって、自分も信じることができるのか。同じものを見ることができないようになったのか。それまで疑いのなかった気持ちに影が差してきたのです。読者は、両親もちひろも純粋にお互いを大切に思う気持ちに心温まりながらも、つかみどころのない不穏な暗雲が立ち込め、気持ちが波立ち、もやもやとしながら考えさせられるのです。(宇津木)