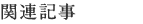『ひかり埃のきみ 美術と回文』
福田尚代 著 平凡社 2,800円+税 装釘 細野綾子
扉の薄紙にのった文字列が、次の頁に透けて見える目次と絶妙に交差して美しい。心静かな日、私がそっと開いてみたくなる特別な本です。
3部構成のその「I」は、福田さんの美術作品からはじまります。頁を半分折り込んだ書物、切りとられた文庫本の背表紙、細かな刺繍がほどこされた書物、消しゴムで彫られた数々の漂着物、原稿用紙に彫刻、粉塵の山……。はじめは些細な行為のはずが、繰り返し時間の経過とともに集積されると、一群れとなってこちら側に語りかけてくる強さがあります。
故郷の郵便局で仕事をしながら、《はじまりからも終わりからも読むことのできる言葉》回文を、彼女は毎日書きました。「II」では、私家版でまとめていたいくつかの回文集から、再考を重ね選出した、7篇の回文へと続きます。回文は言葉遊びの要素が強いものですが、彼女は言葉を砕いて、徹底的に「素」の状態にするまで分解していきます。社会背景に帰属しがちで、束縛された不自由な言葉の枠から一気に解き放たれ、幼い時、音や視覚で感覚的に言葉に触れていた記憶を呼び覚ましてくれます。
「III」の「片糸の日々」で、「I」の美術作品と「II」の回文の連関性が紐解かれ、『ひかり埃(ほこり)のきみ』が意外なことから誕生したのだと感銘を受けます。そこにはあえて触れませんが、私も研ぎすました感性で言葉とその純度に響き合えるようになりたいと願いつつ、「片糸の日々」の冒頭を引用して心に刻みたいと思います。
「幼年時代の視覚に境界などあっただろうか。裏庭へつづく扉をひらくと、ハクモクレンの花に落ちるしずくも、ぬかるみに跳ねる犬も、わたしの濡れた睫毛も、すべてが濃密な空気と溶けあっていた。鳥の声が光にしみ、葉の色にうつる。木漏れ日のひとつひとつが何かをやさしくふりかえりつづける。からだは一枚の花びらとなって庭いっぱいにひろがり、まなざしは地中に沈みかけた陶器のかけらへと吸い込まれてゆく。世界と自分が細かな塵の集積としてひとつになり、霧散する。それらがいっせいに、今この瞬間に起きることとして迫ってくる」(上野)