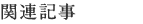『光の犬』 松家仁之 著 新潮社 2,000円+税 装釘 新潮社装幀室
年始めの旅行中、この長編小説を電車で読んでいたら、涙している自分に気づき、あわててゴシゴシと目元をこすりました。しずかな語り口による、深閑とした物語の運びに身をゆだねるうち、最後になるにつれて、ひどく気持ちが昂ってしまったのです。
明治から現代までの100年にわたる時間のなかで、北海道に根ざしたある家族と、彼らを取りかこむ人びとの人生を描いた小説です。彼らはみな、この世に生を受け、さまざまな性格の持ち主に育ち、ある人は、老い衰えて自分を失くして命を終え、ある人は、若くしてバッサリと生を断たれ……と、ひとしく死んでゆきます。
なんて端的にまとめると、味気なく、退屈に思われるかもしれませんが、これがじつに滋味深いのです。なぜなのでしょう?
たとえば、助産婦である祖母に取り上げられて生まれ、聡明でやさしい少女に育つ、添島歩の物語。彼女は思春期になると、牧師の息子であり、母を亡くしている同級生の少年、工藤一惟と恋に落ちます。たがいに必要とし、理解しあっていても、かたく抱きしめあっても、なぜか埋められない空洞がある二人。
やがて二人の道は分かれますが、天文学者となった歩は、30代前半で難病に侵されていることがわかります。病床についた歩が、牧師となった一惟に手紙で託した、最期の願いとは――。
私たちは、思春期の彼女が、名づけられない、名づけたくない強い感情にとらわれて、愛犬とともに涙を流している場面を見ています。天文学者となって、宇宙の星々を観察する日々を送りながら、「どうして自分がいまここにこうしているのか」を考える姿も見ています。だからこそ、彼女が生をまっとうする姿に、強く強く胸をしめつけられる。まるで、自分や、自分の身近な人の人生を目の当たりにするかのように。
そして、一惟には牧師となるまでの人生の物語があり、祖母の添島よねには助産婦となるまでの、歩の弟の添島始には北海道に帰るまでの物語が、暮らしの手ざわりや体温、家族どうしの軋轢などをまじえて描かれます。そこに私たちは目を凝らし、かけがえのない人生とは、自分の人生とは何なのだろうと、ふかぶかと考えたくなるのです。
ああ、小説を読むことは、自分以外の誰かの人生を体験することなんだなあ。最後の頁から目を上げたとき、そんなことをあらためて思いました。ひと口では語れそうになく、しばらくは整理せずにおいておきたい――そんな感情が、胸に熱くじんわりとひろがって――それは、すばらしい体験でした。(北川)