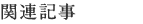平塚らいてうさんから辻村深月さんまで、ずっと続いています。
(定例「随筆」)
「随筆」って、ちょっと古めかしい言い方ですね。エッセイとも言います。
辞書によれば、「自己の見聞・体験・感想などを、筆に任せて自由な形式で書いた文章」とあります。
『暮しの手帖』では、昭和23年の創刊当初からずっと続いている頁です。創刊編集長・花森安治の考えで、各界で活躍する著名人に、専門のことではなくふだんの「暮らし」について書いていただいています。
当時は、森田たま、平塚らいてう、志賀直哉、井伏鱒二、三島由紀夫などの作家をはじめ、芸術家や学者、政治家、主婦などさまざまな方に寄稿していただきました。裁縫や料理など実用の記事だけでなく、読み物も人気の頁でした。なかでも昭和24年の、東久邇成子の「やりくりの記」は、皇族も戦後直後は爪に火を点すような苦労と工夫をして生活していることを伝え、たいへん話題になりました。
いまも、日常の暮らしの中で体験したことや感じたことを、毎号ちがう6人の方々に随筆を書いていただいています。
さて、今号執筆していただいたのは、作家の辻村深月さん、京都大学総長の山際壽一さん、フリーアナウンサーの魚住りえさん、学術書編集者の橘宗吾さん、東京工業大学准教授の伊藤亜紗さん、画家の安野光雅さんです。
直木賞作家の辻村さんのお話は、子どものころ習っていた書道の先生との時間を超えた交流について。ゴリラなど霊長類の研究者である山際さんは、小笠原の父島で経験したエコなトイレのこと。美学と現代アートを専門とする伊藤さんは、目が見えない人の髪についての興味深い考察を。安野さんは、戦後の小さな出会いのなかで聞いた、今も心に深く残る言葉について。
どのお話も、とてもユニークでおもしろいです。実際の「体験」と「感じたこと・思ったこと」だから、いきいきとして情感に満ちた文章を読むと、共感したり、こちらも考えるヒントになったり、ドキドキはらはらしたり、心があたたまったり。
毎号ぜいたくな顔ぶれがそろいますから、どうぞお楽しみに。(担当:宇津木)