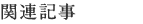揺るぎない暮らしのすがた
――編集長より、最新号発売のご挨拶
窓を開けて仕事をしていると、川辺のグラウンドから、野球少年たちの歓声が聞こえてきます。風が心地よく、見上げる青空は高い。ようやく、ひと息つける季節がめぐってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。
今号の表紙画は、イラストレーターの秋山花さんによる、「on the wind」。黄金色の空を、紙飛行機に乗った2匹の犬がすーっと飛んでいきます。まさに、風まかせの気ままな旅。うらやましいな。
まだいろいろと不自由な状況ですが、せめて心はどこか遠くへ飛ばして、すがすがしい空気を胸いっぱいに吸い込みたい。今号は、そんな思いをこめた特集を組みました。
一つは、巻頭特集の「山の版画家 大谷一良さん」。青や緑を基調とした山々の風景画は、ひととき眺めていると、心が静まっていくようです。
大谷一良さん(1933~2014年)は学生時代、串田孫一さんが部長の山岳部で活動しつつ独学で版画を始め、卒業後は商社マンとして働きながら、文芸誌『アルプ』の表紙画や挿画などを手がけました。超多忙な日々、制作はもっぱら休日をあてて行っていたそうですが、いったいどうしたら、そんな二足の草鞋を履けるのだろうと思います。その作品世界は世事とは無縁、澄みきって見えます。
実在の山ではなく、「自分のなかにある山」を描き続けたという大谷さん。だからこそ、その「山」にはふしぎな抽象性があり、見る人がそれぞれに抱く「山」の記憶やイメージ、何か揺るぎないものを呼び覚ますのかもしれません。
もう一つの特集「手と足と、知恵を使って生きていく」の舞台は、新潟県の山あいにある小さな集落、「中ノ俣」です。著者は、ここに20年来通い続ける写真家の佐藤秀明さん。棚田が広がる山村の四季折々の風景と、そこで暮らすお年寄りたちの日々を撮った写真には、「まだ日本にもこんな暮らしが残っていたのだなあ」と思わされる、驚きと懐かしさがあります。
親しく交流するお年寄りたちは、たとえ足が弱ってきても田畑を懸命に耕す働き者ばかりで、藁細工でも山菜料理でも、ささっと器用にこしらえてしまう。大きな笑顔がすてきで、厳しい自然とともに生きながらも、暮らしをめいっぱい楽しんでいるのです。
佐藤さんは、仲ノ俣に着くと棚田のてっぺんに向かい、そこで集落を見下ろして、流れる空気を感じながらしばし過ごすといいます。
「天日干しされた稲の香りを含んだ風が吹いてくる、秋の昼下がりがたまらなくいい。その甘さを含んだ風は、肺の中に入ってきて体全体に広がってゆく」
ああ、そんな空気を吸い込んでみたいなあ、と思わされる、実感のこもった一節です。
制作中、初校を読みながら気づいたのですが、この特集2本はどちらも、文中の肝となる部分で「揺るがず」「揺るがない」という言葉が使われていました。もしかしたら、いまそうしたものを、私たちが求めているということでしょうか。
自粛生活も1年半になると、外に楽しみを求められないぶん、本当の意味で「暮らしを楽しむ」って何だろうと、よく考えるようになりました。一つにそれは、ともすればただ流れていく一日一日のなかで、誰もが行う日常茶飯にどう工夫して「楽しみ」を見いだせるかな、という「能動的な自分」が必要な気がします。
新米が手に入ったら、おいしく炊いて、シンプルなおかずで味わってみる。手もとにある余った毛糸で、家事に役立つ愛らしい小ものを編んでみる。いまだからこそ、「公助」って何なのか、考えてみる。
今号も、暮らしを能動的に楽しみ、しっかり向き合って考える、そんな特集記事をそろえました。お茶でも淹れて、ゆっくりと読んでいただけたらうれしいです。どうぞ、健やかな日々をお過ごしください。
『暮しの手帖』編集長 北川史織