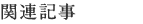ゆるぎないもの
——編集長より、最新号発売のご挨拶
窓を開ければさらりと乾いた風が吹き渡り、エアコンをつけずに一日を過ごせる、そんな心地よい季節になりました。
今年の夏は、酷暑はもちろんのこと、その「不自由さ」においてもなかなかにつらく、我慢くらべのようでしたね。誰もがそれぞれの「不自由さ」と向き合いながら、それでも何かしらの楽しみを見いだそうと工夫して、先の見えない日々を歩んできたような気がします。
私たち編集部は相変わらず在宅勤務を基本に制作を続けていて、この8号ではや3冊目、ビデオ通話の打ち合わせなどはさすがに慣れてきました。それでも、取材や撮影で顔を合わせると、なんだかうれしくて、つい一生懸命に話してしまいます。
同じ空間にいて、たがいの表情を見て、声で空気を震わせて言葉を伝えるのが、なぜこんなによいものなのか。その理由はわからないけれど、ビデオ通話の話し合いが「目的地に向かって脇目も振らずまっしぐら」といった印象なのに対して、じかに会って話すことには、「ゆとり」や「遊び」がある感じでしょうか。ちょっとの寄り道や脱線はゆるされて、会話がふわっと、空間のぶんだけ広がってゆくような。
8号の巻頭記事「どんなときも、絵本を開けば」は、東京・原宿で小さな喫茶店「シーモアグラス」を営む坂本織衣さんに、開店してから24年のあいだ、折々に心を照らしてきた4冊の絵本のことを綴っていただきました。
初めて取材に訪れたのは6月のはじめ。お店のある明治通りは自粛期間前の賑わいを取り戻し、マスク姿の人びとであふれていましたが、坂本さんは3月下旬からお店を休業としたままでした。
「どうしたらいいか、わからないんですよね」
久しぶりにシャッターを開けたという店内で、確か、坂本さんはそんなふうにおっしゃったと思います。嘆くわけでなく、つぶやくように淡々と。
そして、壁一面の本棚にみっちりと詰まった絵本から数冊を抜き出し、それぞれの物語について、ご自分のこれまでの歩みに重ねて語ってくださいました。幼いお子さん2人を育てながらお店を開こうとしていた頃、寝る前の2人に読み聞かせては、親子で心をひとつにした絵本。家事、育児、お店の仕事、ご両親の世話に追われる暮らしのなかで、働き者の主人公に自分を重ね合わせて、その日々を肯定できた絵本……。それらの話は、一つひとつがお店にともる灯りみたいに、ささやかで素朴であったかく、希望を感じさせるのでした。
私たちはたぶん、一人ひとりがこうした、「私はこれがとっても好きなんだ。なぜならば……」という物語を持っていて、たびたび胸の内から取り出しては眺め、ときに誰かに語ったりして、生きる支えとしている気がします。
喫茶店で、見知らぬ人たちに混じって過ごすひとときも。人と目を合わせて話すことも。ひとところに集い、演劇や生の音楽に胸を震わせることも。どんな「好き」も、あっさり簡単に手放していいものなど何一つないんですよね。
自粛期間中に「不要不急」という言葉がよく使われ、「自分の仕事ははたして不要不急か?」なんて自虐めいた話題があちこちで聞かれました。私たちの仕事は、自虐でも謙遜でもなんでもなく、「不要不急である」と言えます。雑誌がなくても、衣食住は成り立ちますから。
けれども、たとえば日々のごはんが栄養をとることだけではなく、心に刻まれ、人とのつながりを感じられるものであるために。自分の手を動かして何かをつくり出す、その楽しみとゆたかさを幾つになっても忘れないために。社会の潮流に対して自分はどう考えるのか、その礎とするために。私たち雑誌ができることはまだあるんじゃないかなと信じ、手探りしながら、この8号を編みました。
なお、連載「からだと病気のABC」は、いつもよりも頁を拡大し、新型コロナウイルスの予防対策を中心にわかりやすくまとめましたので、どうぞご参考になさってください。
心がどことなく張り詰める毎日のなか、この一冊を開いて、ご自分の暮らしでゆるぎないもの、大切にしたいものに思いを馳せていただけたら幸せです。
『暮しの手帖』編集長 北川史織